センターの敷地の西門付近にサルスベリの花が咲いていました。
別名、百日紅といわれるように、夏から秋にかけて長期にわたって紅色の花が咲きます。
ところが今年は、写真にあるように、
8月初旬には咲き誇っていた花も、一月後には花は萎れていました。
酷暑の影響なのでしょうか?

このサルスベリが咲く夏から秋にかけて多く発生する感染症に、レジオネラ症があります。
国立健康危機管理研究機構(JIHS)の感染症情報提供サイトで公表されている内容を要約すると、
- レジオネラ症は主に、夏と秋に多く発生し、特に、7月、9月、10月に報告が集中
- 感染経路は、レジオネラ属菌を含むエアロゾルや塵芥を吸入することで発症し、入浴施設、冷却塔、加湿器等が感染源。原則としてヒト・ヒト感染はない。
- 患者の平均年齢は69.4歳、50歳以上が93.0%を占めており、20歳~90歳は男性の患者が多く、全体では男性が81.9%
※2013年~2023年の届出数をJIHSが分析されています。
IASR 45(7), 2024【特集】レジオネラ症 2013~2023年|国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト
レジオネラ症は、倦怠感や発熱、呼吸器症状を呈し、重症化すると呼吸困難や心筋炎などを合併し、死亡することがある感染症で、以前このブログでご紹介した重症熱性血小板減少症候群(SFTS)や、日本脳炎などと同じ四類感染症です。
今回は、このレジオネラ症を引きおこすレジオネラ属菌の水質検査についてご紹介します。
当センターでは、レジオネラ属菌検査のための検体を受け取ると、まず、LAMP法により遺伝子検査を行います。
LAMP法は、遺伝子を増幅させて菌の存在を確認する方法です。検査機器は、コロナの検査でも使用されていましたPCR検査機器を使用します。おおよそ2時間程度でレジオネラ菌の遺伝子を見つけることができます。
ただし、生菌ではなく死菌の場合にも検出することがありますので、PCR検査で陽性または擬陽性となった場合には、培養法により確定させます。

培養法は、菌を培養して増やして見つける方法です。
培地に濃縮した検体を接種して、37℃で7日間培養します。
レジオネラ属菌を培養すると、ポツポツとした灰白色のコロニーになってきますので、100ml内に10cfu(コロニー形成単位)以上存在すると、レジオネラ属菌と同定します。
この培養の際には、菌を培養しやすくするためのシステイン(アミノ酸の一種)を加えたものと、加えないものを2つセットして比較します。
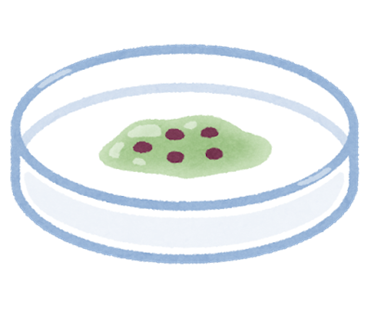
培養まで行うと確定まで1週間以上かかりますが、レジオネラ症は怖い感染症ですし、菌が存在するとなるとお客様にとっては大きな影響となりますので、慎重に判断しています。
今年6月に、大阪・関西万博会場のウォータープラザで、レジオネラ属菌が発生したのでは?ということが話題になっていましたが、当センターと同じように2段階の検査を行った結果、検出限界以下だったようです。
ウォータープラザにおけるレジオネラ属菌の培養法検査結果について | EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト
ホームページのお知らせ欄に「レジオネラ属菌の検査はお済みですか? | 宮崎県公衆衛生センター」の案内を掲載しました。
ご関心のある方は是非、ご一読ください。

